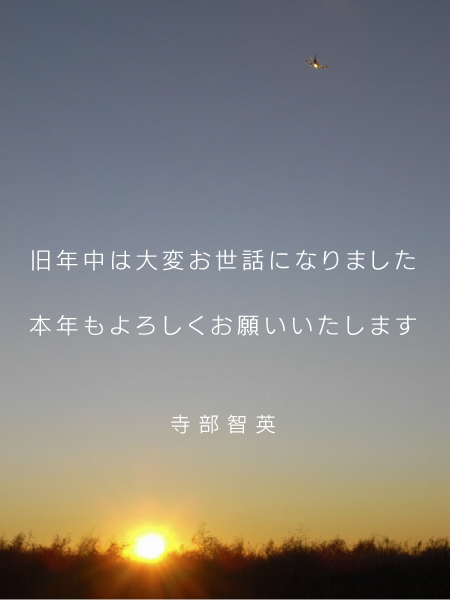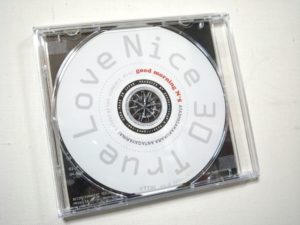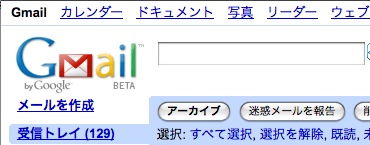料理家のケンタロウさんがやっている、TBSラジオの「ケンタロウのおいしいラジオ」という番組で耳にしたシチューの作り方をもとに、市販のルーを使わずにクリームシチューなどを今年の冬はよくつくるようになりました。
おもな手順
- 多めの油で肉や野菜などの具を炒める
- 小麦粉を投入して炒める(小麦粉大さじ1につき、牛乳1カップ)
- 火を止めて何回かに分けて牛乳をのばしながら注ぐ
- 火をつけて煮込む
- どこかでほどよく塩気を加える
これだけ。これを原則として、いろんな具を入れたりスパイスを入れたりコンソメの素を入れたりすれば自分の味付けになります。僕はまずローリエと黒コショウ、ナツメグは基本として、クリームチーズとか、オイスターソースなんかを入れてみたりしました。
ポイントは、具を炒めたところに直接小麦粉を投入するということ。こうすると小麦粉がダマになりにくいということらしい。
ケンタロウさんは料理の基本というよりは原則のようなものを少ないけど的確なことばでわかりやすく説明してくれるので、それがシンプルであればあるほど応用がいくらでもきくのです。教科書通りになんかやっていられない僕にはとっても相性がいいです。
ベシャメルソース(ホワイトソース)の作り方をすごく短く言うと、「小麦粉を油で炒めて牛乳で溶いたもの」になるそうです。言われてみればそりゃそうなんだけど、結局はこういうことですよ、ってスパッと教えられて、ハッと世界が広がったかんじです。確かにそういうようなことはやるのだけど、それだけでいいんだ。って。
そんなわけでこれからは勝手にケンタロウさんを料理の師匠とさせてもうらうことにします。
師匠は自称、「焦げ目フェチ」だとおっしゃっていて、油の多い肉などを炒める時には焦げ目をしっかりつけないと気が済まないそうです。僕はまだうまく焦げ目をつけられません。

何を入れても合いそうですが、これは白菜、タマネギ、しいたけ、にんじん、オクラ、鶏肉

小麦粉を油で炒める、といえば、カレー(欧風カレー)がそうなのだと気づき、その調子でカレーもつくりました。タマネギ、ピーマン、鶏肉(ササミ)。
シチューでもカレーでも、市販のルーを使わなくてもかなりかんたんにできます。塩や油の量を調整できるので、さっぱりからコテコテまで自由自在です。